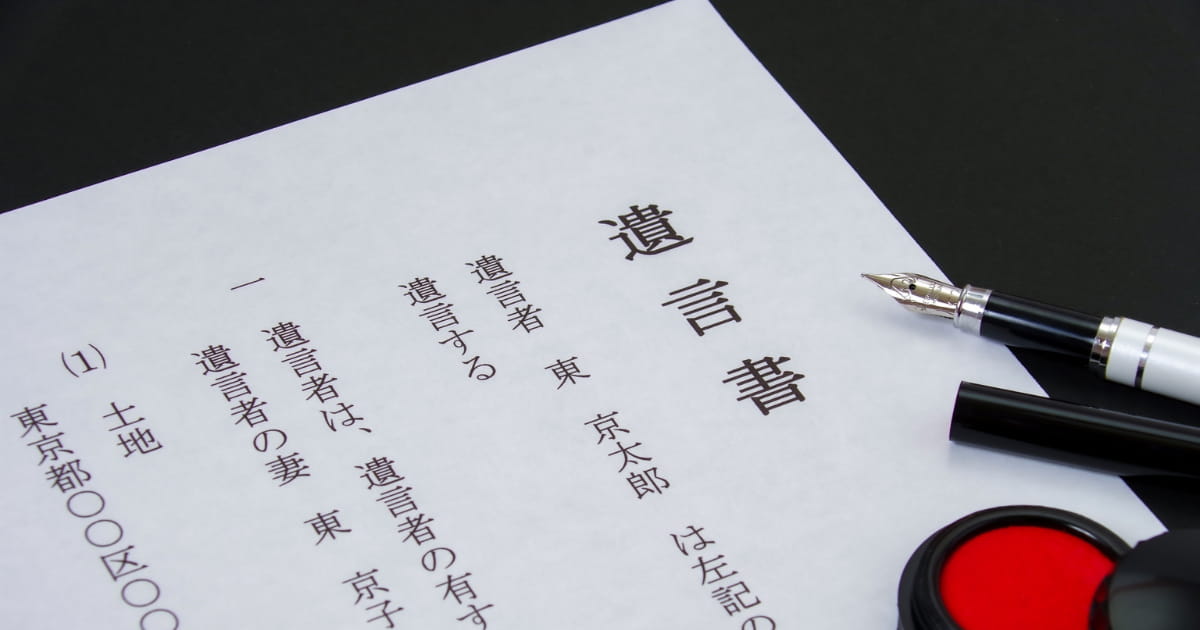遺言書
遺言とは
遺言とは、法律で定められた事項について、遺言者の死亡とともに一定の効果を発生させることを目的とする、遺言者が単独で、法律で定められた方式でする、相手方のない意思表示です。
遺言の目的
「遺言」の最大の目的は、家族を相続トラブルから守ることです!
民法は、ある人が亡くなった時にその人の財産を、「誰が」、「どのような割合」で相続するかを定めています。
これに従うと、例えば「妻(夫)の今後のために財産をもっと残してやりたい」、「家にほとんど寄りつかなかった長男と、献身的に介護してくれた次男の相続分が同じでは二男がかわいそうだ」などの、被相続人の意向に沿わない点が出てくることもあります。民法上は相続人とならない「内縁の妻」や「認知していない子ども」、「老後の世話をしてくれている人」に財産を渡したいという場合もあるでしょう。また、民法上の相続人であっても「あいつにだけは何も渡したくない」ということもあります。
また、相続をした場合には、原則としてすべての財産が、法定相続分に従った割合で共有される状態になります。もちろんのこと、相続人同士で話し合い、法定相続分に従って「誰が」「どの財産を」相続するかを円滑に決めることができれば問題はありませんが、複数の相続人が「土地をもらいたい」と言ったり、相続財産が不動産の場合に「私は現金が欲しい」と言う人が出てきたりして、争いになってしまうことがあります。
以上の問題は、遺留分の定めに反しない範囲で、遺言によって「誰が」、「何を」、「どれだけ相続するか」を明確に定めておくことで解決することができます。
遺言によって、自身が亡くなったあとに、自身の意向を相続に反映させたり、相続をめぐる紛争を防いだりすることが可能となるのです。
遺言は、民法に定める方式に従わなければならず、方式に従わない遺言は無効になってしまいますので、ご注意ください。
法定遺言事項
遺言は法律で定められた事項についてでなければなりません。なぜなら、遺言は、被相続人の一方的な単独の意思表示であり、与える影響が非常に大きく、これを無条件で認めたのでは利害関係人に無用の混乱が生じることになってしまいますので、民法は、遺言事項を定めることとしたのです。この民法で定められた遺言事項を法定遺言事項といいます。
- 相続に関すること
- 遺産の処分に関すること
- 身分に関すること
- 遺言執行に関すること
法定外遺言事項
法定外遺言事項(付言事項)は、法定遺言事項ではないので法的な効力はありません。
付言は、遺言者が何故このような遺言をしたのかという心情を記載し、遺言者亡き後、親族一同仲良く暮らしてほしいという希望などを記載したものです。
法的な強制力はありませんが、付言を読んだ親族が、遺言者の心情を理解して無用の争いを防ぐ効果がある場合もあります。
- 遺言の動機・心情
- 家族の幸福の祈念
- 家族・兄弟姉妹間の融和依頼
- 葬式の方法など
遺言をする必要性が高いケース
①夫婦間に子どもがいない場合
②再婚して先妻の子と後妻がいる場合
③長男の妻に財産を分けてやりたい場合
④内縁の妻がいる場合
⑤その他(事業を承継させたい場合、各人ごとに相続財産を特定して相続させたい場合、相続人がいない場合など)
遺言能力
遺言能力とは、「遺言をすることができる能力」のことをいいます。
民法961条は、「十五歳に達した者は、遺言をすることができる。」と規定しています。
未成年者であっても、15歳に達していれば遺言をすることができます。なお、この場合、親権者や未成年後見人の同意は必要ありません。
また、成年被後見人(民法7条)も、意思能力を欠いていない状況下では、成年後見人の同意を要せずに遺言をすることができます。ただし、事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするときは、医師2人以上の立会いが必要となります。
被保佐人(民法11条)や被補助人(民法15条)も、保佐人や補助人の同意を要せずに遺言をすることができます。
民法962条は、遺言について、制限行為能力者の規定は排除される旨規定しています。
- 未成年者の法律行為(民法5条)
- 成年被後見人の法律行為(民法9条)
- 保佐人の同意を要する行為(民法13条)
- 保佐人の同意を要する旨の審判(民法17条)
意思能力のない者がした法律行為は無効となるので、認知症が進行し重篤な状態となっている場合には、遺言をしても無効となります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が自筆によって遺言を残す方式です。
遺言者が、遺言の全文、日付及び氏名をすべて自書し、押印して遺言書を作成します。
従前は、自筆証書遺言は、これと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合の目録についても自書することが必要でしたが、平成30年の民法改正により、自書は不要となりました。ただし、これは「自書によらない財産目録を添付する方式」のみを例外的に認めるものですので、遺言書(一枚で完結する場合)の一部に「自書」と「自書でない部分」が混在することは認められません。
自筆証書遺言は、遺言公正証書と並んで一般的に多く利用される遺言の作成方式です。
- 原則として内容がすべて自書されている
- 作成日付が自書されている
- 署名がある
- 押印がされている
パソコン等を用いて作成することは自書に当たりません。
自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言は、誰にも知られずに遺言書を作成できるというメリットがあります。
また、遺言公正証書と比較して、作成するための費用がかかりません。
自筆証書遺言のデメリット
最大のデメリットは、形式不備によって無効とされるリスクが高いことです。
特に加除その他の変更には厳格な方式が定められており、これが守られていなかったために遺言が遺言者の意向どおりの効力が発生しない危険があります。
自筆証書遺言の保管制度
平成30年7月、相続法制の見直しを内容とする民法改正がなされ、これに伴って「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(遺言書保管法)が制定され、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が創設されました。
この制度により、遺言書が発見されない、遺言書が変造、隠匿されるといったトラブルを防ぐことが可能となります。
自筆証書遺言の作成者は、法務局に遺言書の原本の保管をゆだねることができます。
保管の申請については、自筆証書遺言の作成者である遺言者本人が自ら法務局に出向いて行わなければなりません。なお、この制度を用いた場合は、家庭裁判所での検認が不要となります。
遺言書保管制度では、自筆証書遺言の方式の適合について、「日付、署名押印があるか」「自筆で書かれているか」といった形式面のみを確認されることになりますので、「遺言の内容」についての相談はできません。
遺言公正証書
遺言公正証書は、証人2名の立ち会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人の面前で、口授し、それに基づいて公証人が遺言者の真意を文章にまとめ、遺言者、証人、公証人が署名押印して遺言公正証書として作成する方式の遺言です。
遺言公正証書のメリット
また、家庭裁判所で検認の手続を経る必要もなく、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することが可能となります。
遺言公正証書のデメリット
遺言の目的となる財産の価額に対応する形で、「遺言公正証書作成の手数料」という費用がかかります。
また、遺言公正証書の作成にあたり、証人2人以上の立会いが必要となります。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言の存在と内容を誰にも知られたくない場合に適した遺言方式であり、公証役場で作成します。
遺言者が遺言内容を秘密にして遺言書を作成したうえで、封印をした遺言証書の存在を明らかにする方法で行われます。なお、実態として利用件数は極めて少ないようです。
秘密証書遺言のメリット
秘密証書遺言は、自書する能力がない場合であっても遺言が作成できるというメリットがあります。パソコンで作成しても、第三者の代書でもかまいません。
秘密証書遺言のデメリット
公証人が遺言内容のチェックを行わないため、遺言の内容に法律的な不備があると無効となる危険性があります。
遺言方式の長所と短所
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 自筆証書 遺 言 | 費用がかからない | 形式不備による無効リスク |
| 公正証書 遺 言 | 紛失、偽造、変造の危険がない 正確な内容のものができる | 費用がかかる 証人が必要 |
| 秘密証書 遺 言 | 秘密保持ができる | 無効リスク 証人が必要 |
報 酬
| 報 酬(税込) | |
| 遺言書の起案及び作成指導 | 30,000円~ |
| 遺言公正証書作成サポート | 50,000円~ |
| 証人(遺言公正証書)(1人) | 11,000円 |
| 任意後見契約書の起案 | 80,000円~ |
| ※ 戸籍謄本・除籍謄本など公的書類の収集にかかる費用については実費請求させていただきます。 ※ 遺言公正証書作成サポートの場合、報酬とは別に公証人への手数料が必要となります。 | |

 行政書士
行政書士遺言書・遺言公正証書作成サポートなら、行政書士ウィル法務事務所にお任せください!