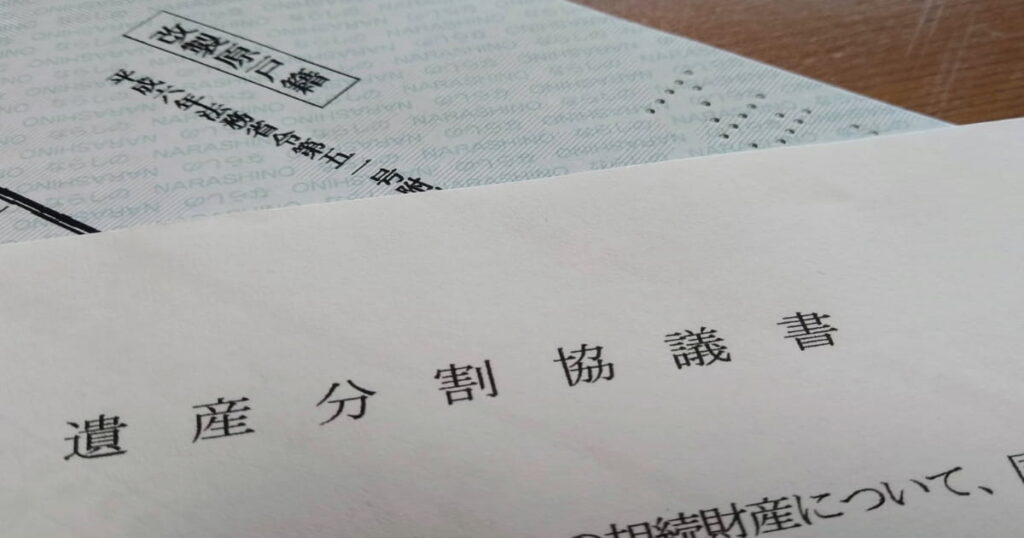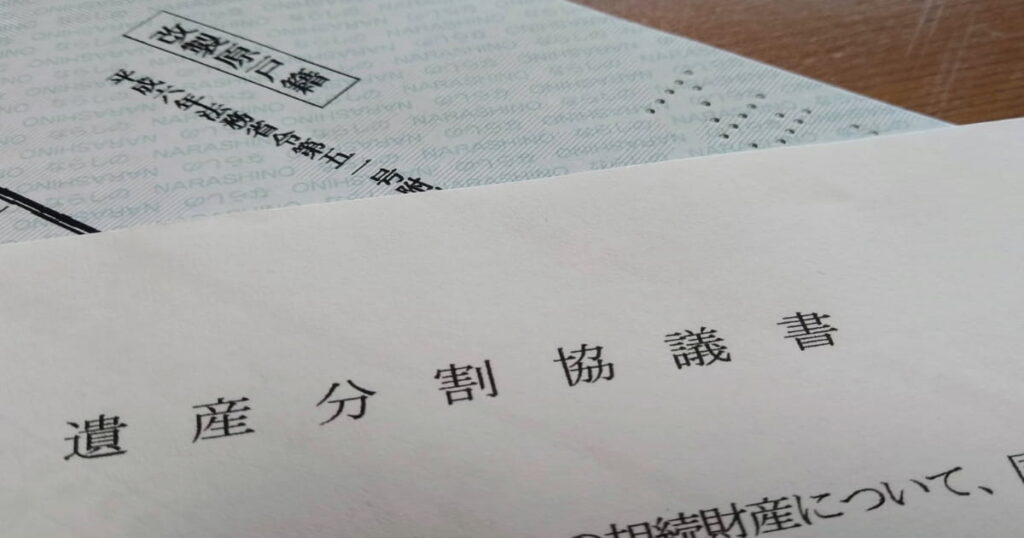相続
遺産分割とは
相続が開始したあと、共同相続人の共有に属している相続財産について、相続財産ごとの権利者を確定させる手続きを「遺産分割」といいます。
被相続人が死亡して、相続が開始すると、被相続人の財産は、相続人に承継されます。
相続人が1人である場合は、原則として、その相続人が被相続人の財産をすべて引き継ぐことになるため問題は生じません。(※特別の遺言がある場合を除きます。)
しかし、相続人が複数いる場合には、複数の相続人(=共同相続人)が、それぞれの相続分に従った共有という形で相続人の財産を共有することになりますので、これを各相続人に分配して帰属させる必要があります。
相続人
被相続人の死亡により、被相続人の財産上の地位を承継する資格を持つ人のことを「相続人」といいます。なお、相続人の範囲・順位は法律によって定められています。
被相続人が遺言を残していない場合、被相続人に属する権利義務は、包括的に相続人に相続されることになります。
遺産分割を行うにあたり、まずは誰が相続人に当たるのかを確認する必要があります。
配偶者相続人
被相続人の配偶者は、常に相続人となります。なお、配偶者については法律上の婚姻関係にあることが必要となります。
血族相続人
血族相続人は、次のとおり順位が定められています。先順位の血族相続人がいない場合(子については代襲相続人もいない場合)、次順位の血族相続人が相続人となります。
第1順位 被相続人の子
被相続人の子は、第1順位の血族相続人になります。「子」には、実子だけでなく養子も含まれます。
第2順位 被相続人の直系尊属
被相続人の直系尊属は、第2順位の血族相続人になり、先順位の被相続人の子(代襲相続人・再代襲相続人を含みます。)がいない場合に相続人となります。
第3順位 被相続人の兄弟姉妹
被相続人の兄弟姉妹は、第3順位の血族相続人となり、被相続人の子(代襲相続人・再代襲相続人を含みます。)も直系尊属もいない場合に初めて相続人となります。
遺産の範囲
遺産分割の対象となる権利
債権、動産、不動産に関する権利など
遺産分割の対象となる債務
金銭債務
遺産分割協議書とは
遺産について、何をどの相続人が取得するかの合意が成立したら、その内容を遺産分割協議書という書面にする必要があります。
遺産分割協議書は、記録を残してトラブルを避けるという意味もありますが、それ以上に不動産の相続登記、銀行預金の名義変更等で必要になるなど、実務面からの作成が求められます。
・預貯金の名義変更または解約
・株式の名義変更
・普通自動車の移転登録
・不動産(土地・建物)の名義変更
上記に該当する場合には、遺産分割協議書の作成が必要となります。
相続税を申告する方は、この遺産分割協議書が「配偶者の税額の軽減」を受けるための添付書類になります。
報 酬
| 報 酬(税込) | |
| 遺産分割協議書原案作成 | 50,000円~ |
| ※ 相続人の数により増減します。詳しくはお気軽にお問い合わせください。 ※ 必要書類等の収集費用(行政庁へ支払う費用を含みます)は、別途必要となります。 | |

 行政書士
行政書士遺産分割協議書の作成や相続手続なら、行政書士ウィル法務事務所にお任せください!
相続登記義務化
不動産を相続したことを知ったときから3年以内に所有権の移転登記(相続登記)の申請をすることが義務付けられます。
遺産分割協議が成立した場合、自身が相続人であることを知り、かつ、相続財産の中に不動産があることを知った日から3年以内に、当該遺産分割協議書に記載された内容について所有権の移転登記(相続登記)を申請しなければなりません。
施行日(2024年4月1日)以前に発生していた相続にも適用されます。つまり、過去に相続した「相続登記が完了していない不動産」についても相続登記義務化の対象となりますのでご注意ください。
正当な理由なく期限内に登記をしなかった場合には、10万円以下の過料が科せられます。